不動産クラウドファンディングで得た分配金──その裏には見逃せない「税金」の壁が立ちはだかります。
「確定申告って必要?」「節税ってできるの?」と悩む方も多いはず。実は、基本を押さえるだけで税負担を減らすチャンスがあります。
本記事では税理士監修のもと、最新の税制に対応した確定申告の方法や節税テクニックをわかりやすく解説。投資リターンを最大化したい方は必見です。
不動産クラウドファンディングと税金の基本

不動産クラウドファンディングの収益には、原則として所得税・住民税が課されますが、その課税方法は「どの所得区分に当てはまるか」で大きく異なります。
主に「雑所得」「配当所得」「不動産所得」の3つの分類が考えられ、それぞれの扱いによって税率や控除の適用範囲が変わります。
分配金はどういう扱いになる?
もっとも多いのが「雑所得」です。多くのクラウドファンディングプラットフォームでは、投資家と運営会社との間に「匿名組合契約」が結ばれる形式が採用されており、その場合、分配金は雑所得として扱われます。
雑所得は給与などの他の所得と合算して課税される「総合課税」となり、累進課税制度のもとで税率は5%〜45%まで変動します。
一方で、一部の案件では「配当所得」として扱われるケースもあります。
これは、上場企業の株式などを通じたREIT型のクラウドファンディングで見られる形式で、この場合、源泉徴収(約20.315%)が行われたうえで、確定申告時に「申告分離課税」または「総合課税」を選択できます。課税方式を選べるという点で、所得の状況に応じた節税戦略が立てやすいのが特徴です。
また、例外的に「不動産所得」として扱われる場合もあります。これは、匿名組合ではなく、不動産所有に近い形態で収益が発生している場合に限られ、経費計上の幅が広いというメリットがあります。
たとえば、プラットフォーム手数料や物件調査費用、セミナー参加費などを必要経費として差し引くことができ、結果として課税所得を抑えることが可能です。
源泉徴収の有無も確認!
さらに、源泉徴収の有無も重要なポイントです。多くのプラットフォームでは、分配金からあらかじめ源泉徴収された金額が振り込まれるため、年間の所得が一定以下であれば確定申告が不要な場合もあります。ただし、年間の分配金が20万円を超える場合や、他の所得と損益通算を行いたい場合は、確定申告が必要になります。
不動産クラウドファンディングの分配金は、案件の契約形態や税務上の取扱いによって所得区分が異なります。自分がどの所得区分に該当するかを正確に把握することが、適切な税務処理と節税の第一歩になります。
次章では、これを踏まえた上での具体的な節税テクニックを紹介していきます。
【2025年版】配当金にかかる税金と節税テクニック

不動産クラウドファンディングの分配金には、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉徴収が課されます。多くのプラットフォームでは、この税金を自動で差し引いたうえで投資家に分配金を支払うため、「税金の処理はもう済んでいる」と思いがちです。
しかし、これには“落とし穴”があります。実際には他の所得との合算や損益通算、控除制度の活用によって税額を抑えられる場合があるため、確定申告をすることで得をするケースも少なくありません。
実践的な節税テクニック
そこで、ここでは2025年の最新制度に基づいた実践的な節税テクニックを紹介します。
節税テク① NISA枠を活用して非課税に
NISA(少額投資非課税制度)は、一定の非課税枠の中で得た投資収益に対して、所得税・住民税がかからない制度です。
一部の不動産クラウドファンディングでは、上場インフラファンドやREIT型商品をNISA口座を通じて購入することが可能になっており、この場合は分配金や売却益が完全に非課税になります。
ただし、すべての案件が対象になるわけではないため、投資前に「NISA対応商品かどうか」を必ず確認しましょう。
節税テク② 法人化による節税スキーム
投資額が大きくなってきた方にとって有効なのが、「法人化による投資」です。個人よりも法人の方が経費計上の自由度が高く、法人税率も一定水準で抑えられるため、長期的に見れば節税効果が期待できます。
たとえば、会計サービス料やセミナー費用、パソコン代などを投資関連経費として処理しやすくなる一方、赤字の場合の損失繰越も活用可能です。
ただし、法人の設立・維持にはコストや手間もかかるため、年間数十万円以上の利益が見込める場合に検討するのが現実的です。
節税テク③ 投資タイミングを分散して税率を平準化
所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がる仕組みです。そこで有効なのが、分配金が集中する年度を避けるために投資のタイミングを分散させる方法です。
たとえば、年末に案件へ投資して分配を翌年に受け取ることで、所得が分散されて税率の上昇を防ぐことができます。
年間を通じて安定的に分配金を得るようスケジュールを調整することで、トータルの税負担を軽減できるのです。
以上のように、不動産クラウドファンディングの税金対策には、制度理解と戦略的な行動が欠かせません。
特に投資額が大きくなるほど、数%の節税が大きなリターンにつながるため、早めの対策が重要です。
次章では、実際の確定申告の手順を税理士の視点からわかりやすく解説していきます。
税理士が教える!確定申告完全ガイド
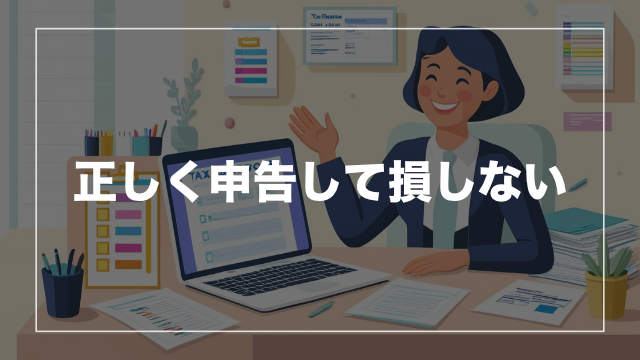
不動産クラウドファンディングで得た収益は、原則として確定申告が必要です。
特に年間20万円以上の分配金を受け取った場合や、複数の所得がある方、損益通算を行いたい場合には、適切な申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。
この章では、税理士の視点から確定申告の実務を分かりやすく解説します。
① 年間収支の把握と必要書類一覧
まずは、1年間の投資収支を正確に把握することが出発点です。不動産クラウドファンディングの各プラットフォーム(CREAL、FANTAS funding、OwnersBookなど)では、年始に「分配金計算書」や「年間取引報告書」が発行されます。これには分配金の総額や源泉徴収された税額が明記されており、確定申告に必須です。
また、支払調書、経費関連の領収書や明細書も忘れずに保存しておきましょう。紙での保存が難しい場合は、PDFで管理しクラウド保存しておくのも便利です。
② 経費計上できる項目とは?
確定申告では、収入から投資に関連する経費を差し引くことができます。たとえば以下のような費用が該当します:
- 投資情報サービスの利用料(有料メディアや分析レポートなど)
- プラットフォームへの振込手数料
- 投資勉強のためのセミナー参加費や書籍代
- 案件現地調査のための交通費や宿泊費
- 税務相談のための顧問料(税理士費用)
経費として認められるには「事業・投資に必要な支出」であることが前提です。プライベートと共用している場合は、合理的な按分が必要となるので、計上の際は注意しましょう。
③ 損益通算の注意点と通算ルール
不動産クラウドファンディングで損失が出た場合、「雑所得」内での損益通算は可能ですが、給与所得や株式譲渡益といった他の所得とは通算できません。
これは「所得区分が異なるため」であり、雑所得同士であっても通算条件が異なる場合があります。
特に注意したいのが、同じプラットフォーム内で黒字と赤字案件が混在しているケースです。損益をしっかり相殺するには、案件ごとの明細をチェックし、合計値としての所得金額を正確に算出する必要があります。
④ e-Taxの使い方と電子申告のメリット
確定申告は、国税庁の「e-Tax」システムを使うことで、自宅からでも簡単に手続きできます。マイナンバーカードとICカードリーダー、または「ID・パスワード方式」でログインすれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が自動作成されます。
電子申告には次のようなメリットがあります:
- 添付書類の一部省略が可能(提出不要)
- 還付処理が早い(紙よりも2〜3週間早いケースも)
- 過去データの自動読み込みで翌年の手間が軽減される
申告ミスを減らし、時間と労力を節約するためにも、電子申告の活用をおすすめします。
適切な記録と正確な申告が、投資の成果を守る最大の防御です。次章では、見落としがちな控除や申告のコツについてさらに深掘りしていきます。
税金控除・申告のチェックポイント集
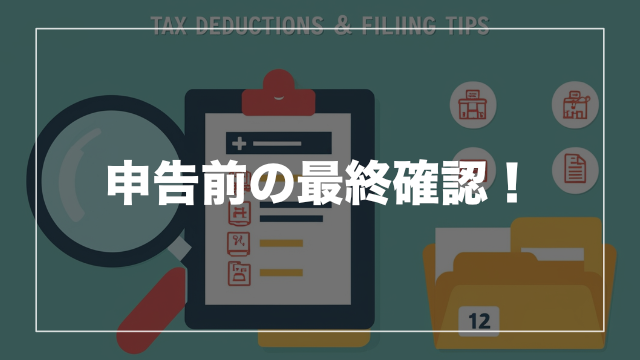
確定申告を行う際には、収入や経費の申告だけでなく、各種控除制度の活用も税負担を軽減するための重要なポイントになります。しかし、これらは意外と見落とされがちです。
ここでは、特に活用したい控除制度や申告方式の選び方、ミスを防ぐための記録管理のコツ、そして申告時によくある失敗例とその対策を解説します。
見落としがちな控除制度
不動産クラウドファンディングによって得た所得が増えた場合、その分「ふるさと納税」や「医療費控除」などの控除枠も広がります。たとえば、ふるさと納税は、課税所得に応じて控除上限額が上がるため、収益が出た年ほど有利になります。
また、年間10万円を超える医療費を支払っている場合は、医療費控除の対象となるため、必ず領収書や明細書を保管しておきましょう。
配当所得の「申告分離課税」と「総合課税」、どっちが有利?
クラウドファンディングの一部では、分配金が「配当所得」として扱われることがあります。この場合、確定申告時に「申告分離課税(税率20.315%)」と「総合課税(他の所得と合算して累進課税)」のいずれかを選ぶことができます。
基本的には所得が低めの方や他に控除が多くある人は「総合課税」の方が有利になりやすく、逆に高所得者や控除の少ない方は「申告分離課税」が有利な傾向にあります。
年収や控除状況によって有利・不利が変わるため、事前にシミュレーションすることが大切です。
書類ミスを防ぐ「記録管理の鉄則」
確定申告では、取引記録や領収書などの証拠書類の保管が重要です。特に複数のプラットフォームを利用している場合、書類の形式や記載内容に違いがあるため、年度ごと・案件ごとにフォルダを分けて管理しておくと安心です。
電子データで受け取った書類は、名前を日付+案件名で統一して保存するなど、検索しやすい命名規則にするのがおすすめ。こうした工夫で、申告直前の混乱を回避できます。
確定申告でミスが多い3つのケースとその対策
確定申告では、以下のようなミスが特に多く見られます。
- 分配金の申告漏れ
→ 各プラットフォームの分配金合計を正確に集計。漏れを防ぐにはExcel等で年間一覧表を作成。 - 経費の過剰・不足申告
→ 明細と領収書が対応しているか必ず確認。按分ルールを守らないと否認されることも。 - 課税区分の誤り(雑所得と配当所得の混同)
→ 契約形態によって異なるため、案件ごとの性質を確認し、所得区分を正確に判断。
これらを踏まえて申告すれば、控除の取りこぼしや誤申告を防ぎ、税負担を最適化できます。次章では、初心者にもわかりやすい申告の手順をステップ形式で紹介します。
初心者も安心!申告手順5ステップ
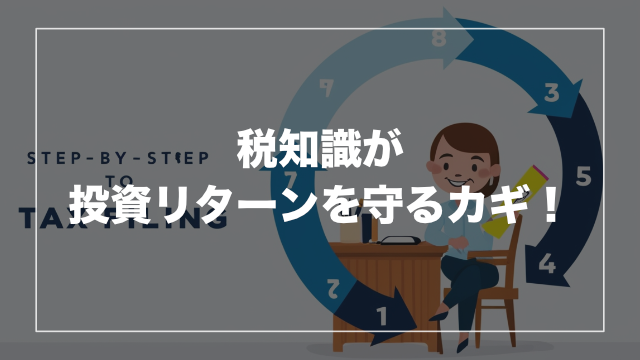
不動産クラウドファンディングで得た分配金は、正しい手順で申告すれば難しくありません。特にe-Taxの活用によって、初心者でもスムーズに申告書を作成できます。
この章では、初めての方でも安心して取り組めるように、申告の流れをステップごとに解説します。
Step1:分配金計算書を揃える
まずは、各クラウドファンディングプラットフォームから発行される「分配金計算書」「年間取引報告書」などの資料を集めましょう。これには1年間で得た分配金の総額や、すでに差し引かれている源泉徴収税額が記載されています。
紙で届く場合もあれば、プラットフォームのマイページからPDFでダウンロードできる場合もあります。案件ごとにファイルを整理しておくと、後の作業がスムーズです。
Step2:申告書B様式+配当所得欄の記入方法
分配金が「配当所得」として扱われる場合、確定申告書B様式の第二表「配当所得の内訳」欄に、プラットフォーム名・分配金の金額・源泉徴収された税額を記入します。
雑所得の場合は、「収入金額等」欄の「その他」に記入する形式です。所得区分を誤ると、税額が不適切に算出されるため、事前に案件ごとの契約形態(匿名組合など)を確認しておきましょう。
Step3:経費入力と最終計算(e-Taxで自動計算活用)
収入に対して必要経費を差し引くことで、課税対象額を抑えることができます。セミナー参加費や振込手数料、投資情報の有料サービスなどが経費対象となることが多いため、領収書や明細を確認して入力しましょう。
e-Taxを使えば、これらの入力に応じて自動的に課税額や還付額を計算してくれるため、手作業によるミスも軽減できます。
Step4:複数プラットフォーム利用者の注意点
複数のクラウドファンディングサービスを利用している場合、それぞれの分配金を合算して申告する必要があります。
たとえば、CREAL・FANTAS funding・OwnersBookなどを同時に利用している場合、すべての計算書から収入と税額を合計し、ひとつの申告欄にまとめて記入します。
プラットフォームごとに分けて申告するとミスの原因になるので注意しましょう。
Step5:申告期限・提出前の最終チェックリスト
確定申告の提出期限は原則として毎年2月16日〜3月15日です。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、余裕を持った準備が大切です。
提出前に以下をチェックしましょう:
- すべての分配金計算書が揃っているか
- 所得区分の選択に誤りがないか
- 経費や控除の記入漏れはないか
- 源泉徴収額を正確に入力したか
- e-Taxまたは紙での提出準備が整っているか
以上のステップを踏めば、初心者でも確定申告は決して難しくありません。正しい知識と準備で、納税額を最適化し、安心して資産運用を続けましょう。
まとめ
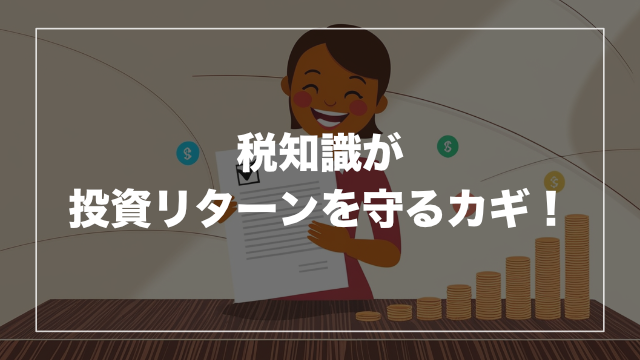
不動産クラウドファンディングで得た分配金には税金がかかりますが、正しい知識を持って対応すれば、税負担を大きく減らすことも可能です。
本記事では、所得区分ごとの違いや源泉徴収の仕組み、NISAや法人化といった節税テクニック、そして確定申告の実践的な手順までを税理士監修のもとで解説しました。
特に初心者の方にとっては、確定申告はハードルが高く感じるかもしれませんが、必要書類を揃えて順を追って対応すれば、決して難しくはありません。また、記録管理や控除制度の活用も重要なポイントです。申告ミスや申告漏れを防ぐためには、早めの準備とe-Taxなどのツール活用が効果的です。
税制は毎年変わるため、最新情報をチェックしながら、確実で有利な申告を心がけましょう。

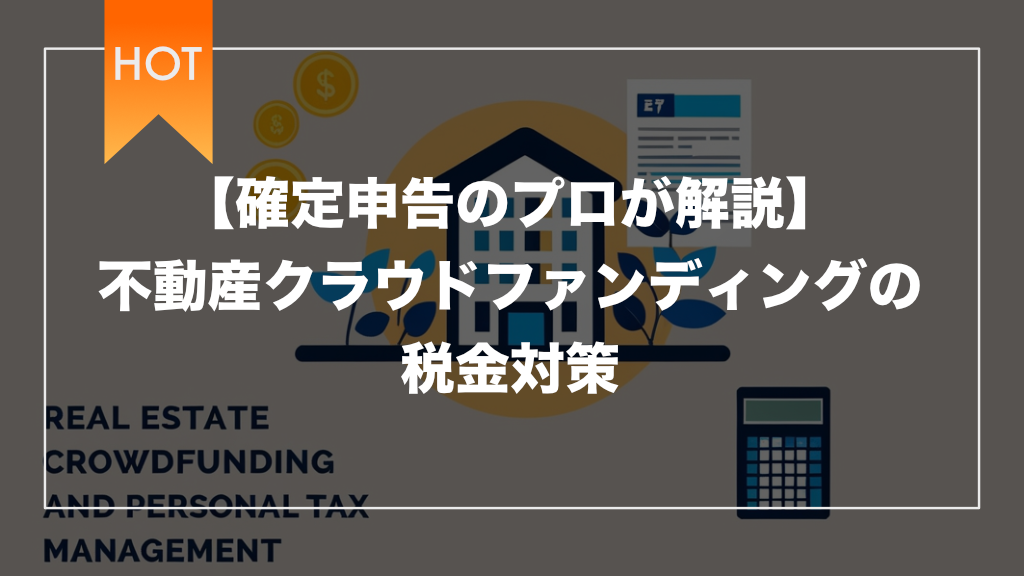




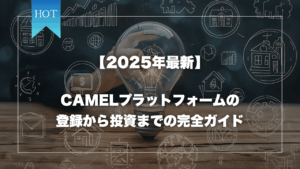
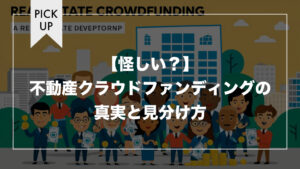


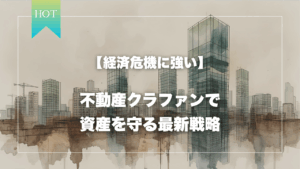
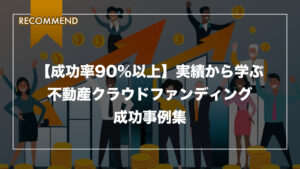


コメント