不動産クラウドファンディングで投資を始めても、確定申告の時期になると「どう処理すればいいの?」と迷う方は多いものです。
2025年は税制改正や電子申告の拡大など、投資家にとって重要な変更点が登場します。
本記事では、分配金の所得区分や必要書類、節税の工夫まで、初心者にもわかりやすく徹底解説。不動産クラウドファンディングを活用するうえで欠かせない確定申告のポイントを最新情報とともに紹介します。
不動産クラウドファンディングの確定申告で損しない方法とは?

不動産クラウドファンディングの投資家が増えるにつれて、「分配金はどう申告するの?」「税金を抑える方法はあるの?」といった疑問を持つ方が多くなっています。
実際、分配金はファンドの仕組みによって税務上の扱いが異なり、ここを理解していないと税負担が増える可能性があります。
2025年は税制改正により、電子申告の義務化範囲や課税方式の取り扱いが整理される見込みですので、正しい知識を持って臨むことが重要です。
不動産クラウドファンディングの収益
まず、不動産クラウドファンディングの収益は大きく分けて「雑所得」「配当所得」「不動産所得」のいずれかに分類されます。
多くの匿名組合型ファンド(CAMELやCREALなど)が該当するのは「雑所得」で、分配金は20.315%(所得税+住民税)が源泉徴収されたうえで入金されます。この仕組みにより、投資家は複雑な計算をしなくても一定の納税が完了している点が安心材料です。
一方で、COZUCHIの一部任意組合型ファンドのように「不動産所得」に区分される場合もあり、この場合は損益通算が可能になります。
たとえば赤字が出た場合、給与所得や事業所得と相殺できるため、節税の余地が広がります。
経費計上に要注意!
次に見落とされがちなのが「経費計上」です。不動産クラウドファンディングの投資は、インターネットを通じて行うため、情報収集にかかった通信費や投資関連書籍の購入費、セミナー参加費なども条件次第で経費として計上可能です。
これらを適切に申告すれば、課税所得を減らすことができ、合法的に税負担を軽くできます。特に複数の案件に投資している方は領収書やレシートを整理し、確定申告に備えることをおすすめします。
また、複数のプラットフォームを利用している場合は、必ず全体を合算して申告する必要があります。一部だけを申告してしまうと、税務調査の対象になる可能性もあります。
クラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使えば、複数プラットフォームのデータを一元管理でき、申告漏れを防ぐことができます。
このように、収益区分の理解・経費計上・取引データの一元管理を徹底すれば、確定申告は決して難しくありません。
特に初心者は、各プラットフォームが提供する分配金明細やガイドを確認しつつ、必要に応じて税理士に相談することで、安心して確定申告を行うことができます。適切な申告は投資の利益を最大化する第一歩といえるでしょう。
2025年の確定申告はこう変わる!初心者でも安心の手順解説
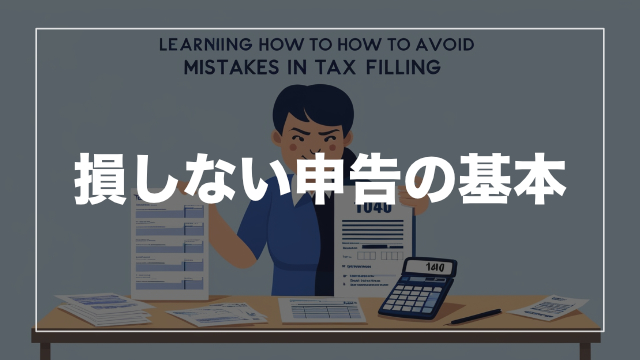
2025年の確定申告で特に注目すべきポイントは、配当金に関する制度改正と電子申告(e-Tax)の拡大です。これまで紙の申告書を使うことが一般的だった方も、今後は電子申告がより広く求められる見込みです。
たとえば、不動産クラウドファンディングによる年間配当収入が一定額を超える場合には、原則としてe-Taxを利用することが推奨されます。
紙での申告も可能ですが、理由書の提出が必要になり、実務的には電子申告に慣れておくのが得策といえるでしょう。
配当所得の扱い方
次に、配当所得の扱い方にも変更が加えられる予定です。従来は「総合課税」と「申告分離課税」を投資家が選択できましたが、改正後は投資額や収入規模に応じて自動的に区分される仕組みが検討されています。
具体的には、年間投資額が一定額を超えると申告分離課税、それ以下であれば総合課税が適用されるイメージです。この変更により、所得額に応じたより公平な課税が行われることが期待されます。
申告の手順
- プラットフォーム(CAMEL、CREAL、FANTAS fundingなど)から送付される「分配金計算書」や「支払調書」を受け取る
- マイナポータルを通じてe-Taxにアクセスし、必要事項を入力
- 配当所得の欄に、プラットフォーム名・分配金額・源泉徴収額を記入
- 所得区分に応じて課税方式が自動振り分けされるので確認
- 必要な控除(医療費控除、寄付金控除など)を追加入力
- 内容確認後、電子署名を付与して送信
この流れに沿って進めれば、初心者でも迷うことなく確定申告が可能です。特にe-Taxでは源泉徴収済みの税額が自動反映されるため、入力ミスを防げるのが大きなメリットです。
「少額投資非課税制度」の拡充
さらに、2025年からは「少額投資非課税制度」の拡充が検討されています。これは年間20万円までの投資額に対する配当金が一定期間非課税となる制度で、不動産クラウドファンディングにも適用される予定です。
適用を受けるには専用の口座開設や事前申請が必要となるため、早めの準備をしておくと安心です。
主要プラットフォームでは、投資家が迷わないよう専用の申告ガイドを用意しています。たとえばCAMELでは分配金明細をわかりやすく整理して提供しており、初心者でも数字をそのまま入力するだけで申告作業が進められます。
申告に不安を感じる方は、こうしたサポートや税理士相談サービスを積極的に活用しましょう。
適切に申告を行うことで、過払い税の還付を受けられたり、将来の税務調査リスクを避けられたりします。2025年の変更点を押さえ、早めに準備することが投資家としての安心につながります。
確定申告の落とし穴と節税テクニック

不動産クラウドファンディングで得た収益を申告する際、投資家がつまずきやすいポイントがいくつかあります。特に注意すべきは「収益区分の誤り」と「複数プラットフォームを利用している場合の合算漏れ」です。
これらを正しく処理できていないと、思わぬ追徴課税につながる可能性があるため十分な注意が必要です。
収益区分について
まず収益区分について見てみましょう。不動産クラウドファンディングの収益は、主に「分配金」と「償還益」に分かれます。分配金は雑所得または配当所得として扱われ、原則20.315%が源泉徴収されます。
一方で、満期時に元本以上の金額が返還されて得られる償還益は譲渡所得として扱われることが多く、保有期間によって税率が異なります。
ここを混同すると税額が過大または過小になってしまうため、必ずファンドの契約形態を確認してから申告しましょう。
複数プラットフォーム利用時の合算漏れ
次に、多くの投資家が陥りがちなのが「複数プラットフォーム利用時の合算漏れ」です。例えばCAMELやCREAL、COZUCHIなど複数サービスに分散投資している場合、それぞれから発行される「分配金計算書」や「支払調書」を合算して申告する必要があります。
一部だけを申告すると、後に税務調査で指摘される可能性があり、余計なリスクを背負うことになってしまいます。クラウド会計ソフトを使って取引履歴を一元管理しておくのが有効です。
節税テクニック
ここからは節税テクニックについて紹介します。まず経費計上です。投資に関連する書籍やセミナー費用、会計ソフトの利用料などは、条件を満たせば必要経費として認められる場合があります。
これらを申告に反映させることで、課税対象額を抑えることが可能です。
また、損益通算も有効な節税手段のひとつです。特にCOZUCHIの任意組合型ファンドのように「不動産所得」に分類される案件では、赤字が出た場合に給与所得や事業所得と相殺できる可能性があります。
これにより納税額が軽減されるため、投資で損失が出たときでも無駄にはなりません。一方で、雑所得に分類される匿名組合型ファンドの場合は損益通算の範囲が限定されるため、自分の投資商品がどの所得区分にあたるのか把握しておくことが欠かせません。
還付を受けられる可能性
さらに、源泉徴収された税金が過大になっているケースでは、確定申告によって還付を受けられる可能性もあります。特に給与所得者で年収が一定水準以下の方は、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくるケースが多いのです。
「源泉徴収があるから申告しなくてもいい」と思い込まず、一度試算してみることをおすすめします。
このように、確定申告の「落とし穴」を避けると同時に、合法的な節税テクニックを取り入れることで、投資の収益性はさらに高まります。プラットフォームが提供する資料を活用しつつ、必要に応じて税理士のアドバイスを受けながら、適切な申告を心がけましょう。
確定申告の期限
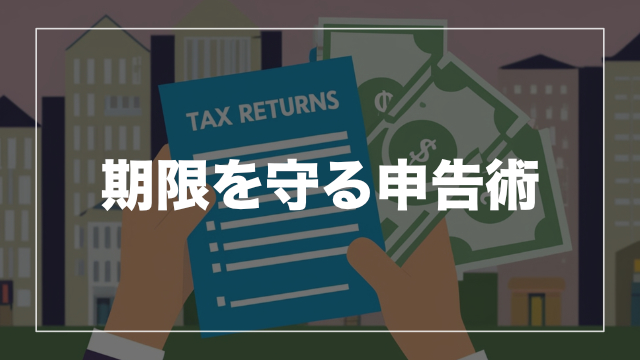
確定申告のシーズンが近づくと、「まだ時間がある」と油断してしまい、直前になって慌てる方も多いのではないでしょうか。不動産クラウドファンディングで得た収入を申告する場合、期限を守ることが何よりも大切です。
2025年も例年通り、確定申告期間は 2月16日から3月15日 までと想定されています。この期間を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。
不動産クラウドファンディングの分配金の扱い
不動産クラウドファンディングの分配金は「雑所得」または「配当所得」に分類されることが多く、場合によっては「不動産所得」となることもあります。
COZUCHIやCREAL、CAMELといったプラットフォームが提供するファンドは、それぞれ契約形態によって扱いが異なるため、必ず発行される「分配金計算書」や「支払調書」を確認しましょう。特に匿名組合型ファンドでは、源泉徴収済みの税額が記載されているため、その金額をもとに正確に入力することが重要です。
申告手続きをスムーズに進めるためには、事前の整理が欠かせません。まず、投資したすべてのプラットフォームからの書類を集め、年度ごとにまとめておきましょう。
複数の案件に投資している場合、合算して申告する必要があるため、1件でも漏れると申告不備となる可能性があります。こうした管理にはクラウド会計ソフトを利用するのがおすすめです。f
reeeやマネーフォワードといったサービスを使えば、自動で仕訳や集計を行えるため、申告書作成の負担が大きく軽減されます。
電子申告(e-Tax)
電子申告(e-Tax)を利用すれば、自宅から申告できるうえ、還付金の受け取りも早くなるというメリットがあります。ただし初めて利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダーの準備が必要です。
スマートフォン対応のマイナポータルアプリを利用すれば、カードリーダーがなくても申告可能となるので、事前に環境を整えておくと安心です。
また、不動産クラウドファンディングで得た年間所得が20万円を超える場合は必ず申告が必要です。たとえ会社員や公務員で給与所得が源泉徴収されている方でも、副業収入にあたるため確定申告を避けることはできません。
少額だから大丈夫と油断せず、年間の合計額で判断するようにしましょう。
税理士に相談しよう
初めての申告で不安がある方は、税理士への相談も検討してください。日本税理士会連合会や各地域の税理士会のウェブサイトから、確定申告相談を受け付けている税理士を探すことができます。
専門家のサポートを受ければ、節税のアドバイスも得られるため、投資効率をさらに高められるでしょう。
期限を守り、正確に申告を行うことは、投資を継続するうえで欠かせない基本です。早めの準備と正しい知識で、安心して確定申告に臨みましょう。
確定申告は必須なのか?
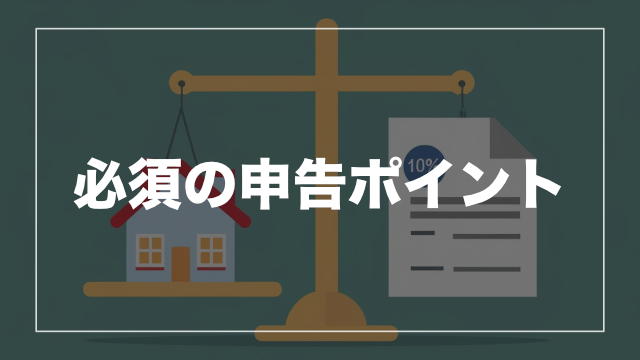
不動産クラウドファンディングで得た利益は、原則として確定申告の対象となります。特に20万円を超える収入がある場合は、給与所得者であっても必ず申告しなければなりません。
副業感覚で少額から投資を始めた方も、年間で合算すると基準を超えるケースが多いため注意が必要です。
収益の税務上の区分
収益の税務上の区分は、ファンドの仕組みによって異なります。CAMEL(キャメル)やCREALなどの匿名組合型ファンドでは「雑所得」として扱われ、分配金に対して20.315%(所得税+住民税)が源泉徴収されたうえで入金されます。
一方、COZUCHIの一部の任意組合型ファンドでは「不動産所得」となるため、損益通算が可能です。また、ファンドの償還益(元本超過分)は譲渡所得として扱われ、保有期間によって税率が変わる点も理解しておきましょう。
源泉徴収が行われている場合でも、確定申告は不要とは限りません。総合課税を選択することで、所得金額が一定水準以下の方はすでに引かれている税額の一部が還付される可能性があります。
たとえば給与所得と合わせても課税所得が低めの方は、確定申告を行うことで払い過ぎた税金が戻るケースが多いのです。したがって「源泉徴収されているから安心」と思わず、一度シミュレーションしてみることが大切です。
損失が生じた際には?
また、損失が発生した場合の扱いにも注意が必要です。匿名組合型ファンド(雑所得)で発生した損失は、原則として他の所得と損益通算できません。
しかし、不動産所得に区分される任意組合型ファンドでは、給与所得や事業所得と通算可能な場合があり、節税に活用できます。自分の投資案件がどの所得区分に該当するかを事前に確認することが重要です。
準備は万全にしておこう
申告書類の準備も忘れてはいけません。必要書類にはマイナンバーカード、各プラットフォームが発行する分配金計算書や支払調書、投資履歴がわかるレポートなどがあります。e-Taxを利用する場合でも、これらを整理・デジタル化しておけば手続きがスムーズに進みます。
クラウド会計ソフトを利用すれば、複数プラットフォームの取引データを自動で集計でき、申告作業の負担を大きく減らせます。
まとめ

不動産クラウドファンディングは、少額から始められる手軽さと安定的な利回りが魅力ですが、確定申告を正しく行うことが利益を守るうえで欠かせません。
2025年は電子申告の利用範囲拡大や課税方式の整理など、投資家に影響する制度改正が予定されており、早めに対応準備をしておくことが安心につながります。
分配金の所得区分はファンドの形態によって「雑所得」「配当所得」「不動産所得」と異なり、さらに償還益は譲渡所得として扱われます。この区分を誤ると課税額が変わってしまうため、必ず各プラットフォームが発行する分配金計算書や支払調書を確認することが重要です。
CAMEL(キャメル)をはじめとする主要サービスでは、初心者でも迷わないように明細やガイドを提供しているので、積極的に活用しましょう。
制度改正や最新の税制情報をチェックし、適切な申告を続けることで、不動産クラウドファンディングを安心して長期的に活用できるでしょう。




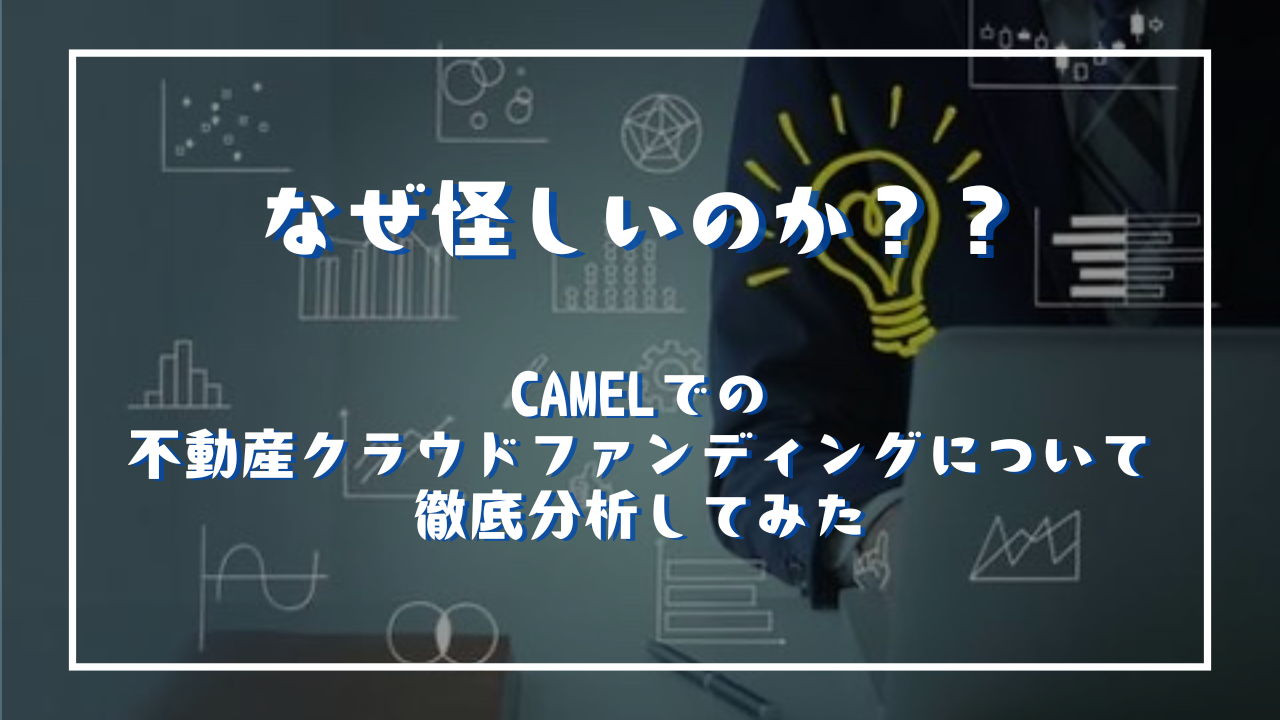




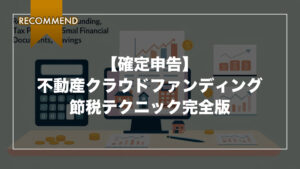
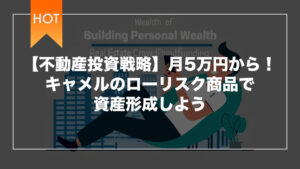

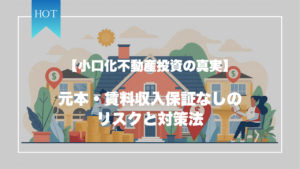

コメント